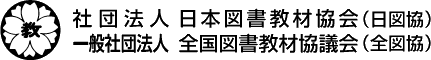HOME>協会概要 [ 概要・沿革 ]
概 要
1955年(昭和30年)、国会で教科書や図書教材の内容や販売方法が問題(憂うべき教科書の問題)となり、同年、図書教材を発行・供給していた教材出版社と販売店が集い、「日本図書教材直販協会」を設立しました。
その後、1958年には、文部省より教材出版社の団体として「社団法人日本図書教材協会(日図協)」が認可され、それにともない販売店と日図協加盟教材出版社によって全国図書教材販売協議会(全販協)も設立されました。
1968年(昭和43年)、図書教材の質的向上をはかる事業を強化するため、日図協より研究部門を独立させて「財団法人図書教材研究センター」が設立されました。
以降、図書教材の研究、作成、普及、供給……各分野において3団体は、それぞれの役割を果たしてきました。
2010年(平成22年)、公益法人制度改革により、全販協は組織改革をするとともに、「一般社団法人全国図書教材協議会(全図協)」となりました。また、2011年には、日図協が財団法人図書教材研究センターを吸収合併し、合併後の新日図協は2013年には一般社団法人となる予定です。
沿 革
[備考]
- 略記の意味
- (社)…
- 社団法人日本図書教材協会
- (財)…
- 旧財団法人図書教材研究センター(1968年9月〜2011年8月)
- (全)…
- 一般社団法人全国図書教材協議会
(2010年9月まで全国図書教材販売協議会) - (学)…
- 日本教材学会
- (著)…
- 教材等著作権保護委員会
- (
 ・・・)をクリックすると、その項目の詳細な資料がご覧になれます。
・・・)をクリックすると、その項目の詳細な資料がご覧になれます。
1955(昭和30)年 |
8月 |
小・中学校用教材を作成・販売する出版社と販売店により、日本図書教材直販協会が設立される。創立の頃。 |
|---|---|---|
1956(昭和31)年 |
12月 |
図書教材新報創刊号 |
|
2月 |
直販協会第1回通常総会及び支部長会議 |
| 1957(昭和32)年 | 11月 |
はじめての編集者講習会開催。 |
1958(昭和33)年 |
8月 |
(社)(全)直販協会が出版社の団体として組織替えし、文部省より社団法人の認可を得て、社団法人日本図書教材協会が設立される。これにより、販売店の組織は、支部から都道府県図書教材販売協会と改組し、出版社と販売協会とにより、全国図書教材販売協議会が設立される。 |


全販協第1回総会 協会の社団認可祝賀会参加者 |
||
1959(昭和34)年 |
|
◇公正取引委員会の指導により、再販契約の締結が進む。 |
1963(昭和38)年 |
|
◇公正販売(リベート撲滅)運動盛り上がる。 |
|
12月 |
(社)はじめての営業社員研修会開催。 |
1964(昭和39)年 |
|
◇教科書会社のテスト発行で紛糾。 |
|
3月 |
文部省・福田初中局長より「学校における補助教材の取り扱いなどについて」の通達。 ◇複写複製被害広がる。 |
1965(昭和40)年 |
3月 |
教科書会社が教材会社を著作権法違反で提訴(仮処分)。 |
|
7月 |
教科書会社の訴えが却下(東京地裁民事第29部) |
|
11月 |
東京都・小尾教育長より「入試準備教育の是正について」の通達。 |
1966(昭和41)年 |
7月 |
(社)学校教材調査会スタート。のち財団へ移管。 |


学校教材調査会第1回総会と調査結果発表会 |
||
1967(昭和42)年 |
8月 |
教科書会社が教材会社を著作権法違反で提訴(損害賠償等請求)。 |
1968(昭和43)年 |
2月 |
教科書会社が教材会社を著作権法違反で東京地検に告訴。しかし和解。 |
|
9月 |
(財)図書教材研究センター設立。 |
|
12月 |
教科書会社と教材会社の著作権裁判が和解。以降、友好関係が確立される。 |
1969(昭和44)年 |
1月 |
(財)図書教材研究センタービル竣工。 |
1970(昭和45)年 |
1月 |
(財)全国教育研究所連盟に加盟。 |
|
2月 |
(社)教科書会社代表と謝金贈呈に関する契約を締結。 |
|
7月 |
(財)「図書教材利用の理論と実際」を刊行。 |
1971(昭和46)年 |
|
(全)5銭拠出事業を開始。 |
1972(昭和47)年 |
12月 |
(著)教材等著作権保護委員会を設置。委員長に小林尋次氏就任。 |
1973(昭和48)年 |
1月 |
各出版社、見本に教材等著作権保護委員会名の「複製禁止について」のチラシを挿入。 |
1975(昭和50)年 |
6月 |
(社)家庭訪問販売規制法に対し、図書教材販売を除外するよう陳情。 |
1976(昭和51)年 |
|
◇偏差値テスト・模擬テスト(業者テスト)批判広がる。 |
|
8月 |
(財)「"学力テスト"と"偏差値"について」を発表。 |
|
10月 |
(社)(財)「『業者テスト』についての正しい解説書」を作成・配布。 |
|
11月 |
(社)訪問販売規制法施行に対し、教材業界を対象外とするよう重ねて陳情。 |
1978(昭和53)年 |
3月 |
(著)教材等著作権保護委員会を再編。委員長に水田耕一氏就任。 |
1980(昭和55)年 |
|
◇ファクシミリの導入進む。販売店からの発注は、電報→電話→ファクシミリへ。 |
1984(昭和59)年 |
4月 |
(全)図書教材業における経済上の利益の提供等に関する自主基準を施行。 |
1985(昭和60)年 |
|
◇児童数減少が大きな課題となる。 |
1989(平成元)年 |
|
◇バブル景気で、原料費高騰と人手不足の影響が深刻に。 |
|
1月 |
(学)日本教材学会設立。 会長に辰野千壽氏が就任。
(学)日本教材学会設立総会 |
3月 |
(社)創立30周年記念式典を開催。 |
|
 
創立30周年記念誌「築く」 創立30周年記念式典・文部大臣挨拶 |
||
4月 |
◇消費税施行。直販業界は内税方式を採用。 |
|
|
(全)各協会ブロックに中学部会の設置を進める。 |
|
11月 |
(学)第1回研究発表大会開催。 |
|
| 1991(平成3)年 |
|
(全)雲仙普賢岳噴火被害に際し、加盟社に呼び掛け、教材を無償提供。合わせて、被害援助募金を実施。 |
7月 |
(全)全国中学部会長会議を設置。 |
|
| 1992(平成4)年 | 2月 |
(全)業界の未来を考える委員会を設置。 |
3月 |
(社)ジャスラックとの間で「音楽ワークブックの取り扱いに関する覚書」を締結。 |
|
4月 |
◇小学校各社、グリーンマーク運動に参画。 |
|
9月 |
◇学校に週5日制導入(第2土曜休日)。 |
|
| 1993(平成5)年 | 2月 |
◇文部省、業者テスト・偏差値排除を通知。 |
3月 |
(全)学校直販教材と業者テストの違いや評価に関する解説書を作成・配布。 |
|
4月 |
◇中学校各社、グリーンマーク運動に参画。 |
|
7月 |
(財)『授業と教材−教材の正しい理解と活用のために』を刊行。以後、小・中学校の新任教員に継続して無償で提供。 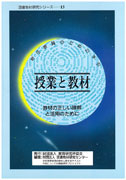
「授業と教材」 |
|
9月 |
(学)日本学術会議の学術研究団体として登録。 |
|
| 1994(平成6)年 |
|
◇再販制度の見直し議論が活発化。 |
12月 |
(社)日本写真家協会との間で「写真の取り扱いについて」の協定を締結。 |
|
| 1995(平成7)年 |
|
(全)阪神・淡路大震災救援募金を実施。 |
| 1996(平成8)年 | 5月 |
(社)創立40周年記念式典を開催。 
創立40周年記念式典 |
7月 |
(社)第3回数学・理科教育調査の国内調査結果に関する編集者研修会を開催。 |
|
11月 |
(全)「都道府県図書教材販売協会の活動」のパンフレットを作成・配布。 |
|
| 1997(平成9)年 | 7月 |
(財)小学校英語教材の在り方に関する研究についての編集者研修会を開催。 |
| 1998(平成10)年 | 7月 |
(社)第3回数学・理科教育調査の国際比較に関する編集者研修会を開催。 |
12月 |
(全)公益法人化研究特別委員会を設置。 |
|
| 1999(平成11)年 | 3月 |
(社)新学習指導要領(小学校)の趣旨徹底のための編集者研修会を開催。 |
7月 |
(社)日本児童出版美術家連盟との間で「絵画の取り扱いについて」の協定を締結。 |
|
9月 |
(社)小学校国語教科書著作者の会との間で「小学校国語教科書準拠教材における作品使用についての協定書」を締結。 |
|
10月 |
(社)新学習指導要領(中学校)の趣旨徹底のための編集者研修会を開催。 |
|
| 2000(平成12)年 | 1月 |
(全)リサイクル研究委員会を設置。 |
3月 |
(全)採用促進のため「学校教育と図書教材−学校教材のご採用にあたって」のパンフレットを作成・配布。 |
|
6月 |
(全)大阪・池田小学校での児童殺傷事件を契機に全教委あて文書「学校への訪問に関するお願いについて」を送 付。 |
|
8月 |
(社)協会ホームページを開設。 |
|
9月 |
(全)三宅島の雄山噴火による全島避難に際し、加盟社に呼び掛け、教材を無償提供。 |
|
| 2001(平成13)年 |
|
(社)業界ネットワーク受発注VAN稼動開始。 |
3月 |
(社)日本文藝家協会との間で「小学校、中学校及び高等学校用図書教材等における文芸著作物使用についての協定書」を締結。 |
|
|
◇再版制度の存続が確定。 |
||
6月 |
(社)新指導要録趣旨徹底のための編集者研修会を開催。 |
|
7月 |
(社)国語教科書掲載作品著作権処理のデータベースを構築、運用開始。 |
|
|
(社)国際教育到達度評価学会の国際比較に関する編集者研修会を開催。 |
||
|
(全)学校訪問規制強化対策として身分証明書つきパンフレット「歴史の重みの上で−今こそ、学校直販業界!」を会員に作成・配布。 |
||
|
(全)小規模校対策委員会を設置。 | ||
| 2002(平成14)年 | 1月 |
(全)リサイクル研究委員会をReCo実行委員会に再編。 |
3月 |
(社)業界統一商品マスタの無料提供開始。 |
|
4月 |
◇ゆとり教育と自ら学ぶ力の育成、週5日制の完全実施、学習内容の3割削減、総合的な学習の時間の新設、各種制度・規制の弾力化を盛った新教育課程実施。 |
|
|
(全)リサイクルシステム「ReCo」本格稼動。 |
||
| 2003(平成15)年 | 1月 |
(全)生命共済制度の引き受け会社がジブラルタ生命(旧・協栄生命)から財団法人全国中小企業共済財団へ移行。 |
7月 |
(全)小規模校対策委員会、本報告書「図書教材業界の危機、そして学校教育の危機」を作成・配布。 |
|
|
(全)全国小学部会長会議(全小会議)を設置。 |
||
11月 |
(著)教材等著作権保護委員会を再編、委員長に岡邦俊弁護士が就任。 |
|
12月 |
(全)構造改革委員会を設置。 |
|
|
◇学習指導要領の一部改正。「確かな学力」を育成し、「生きる力」をはぐくむという指導要領の更なる定着を進める。総合学習の時間の一層の充実や、習熟度別指導、補充的な学習や発展的学習などの指導の充実が盛りこまれる。 |
||
| 2004(平成16)年 | 3月 |
(社)学習指導要領一部改訂の趣旨徹底のための編集者講習会を開催。 |
7月 |
(全)平成16年度より、理事会・幹事会を年5回から年4回へ変更。ブロック小・中学部会長会議を年2回開催。また、全中会議の全国会議を中止。 |
|
8月 |
(全)新潟、福井水害に際し、加盟社に呼び掛け、教材を無償提供。 |
|
|
(社)教学図書協会との契約内容を大幅に見直し、「教科書準拠教材への教科書利用に関する基本契約書」を締結。 |
||
9月 |
(社)NPO法人日本文藝著作権センターと提携して、教材に関する文芸著作物使用に関する編集者研修会を開催。 |
|
10月 |
(全)新潟中越地震に際し、加盟社に呼び掛け、教材を無償提供。合わせて、新潟中越地震義援金を実施。 |
|
11月 |
(全)財団法人古紙再生促進センター主催の紙リサイクルセミナーで、ReCoを事例発表。 |
|
| 2005(平成17)年 | 1月 |
(社)機関紙「図書教材新報」一時休刊。 |
2月 |
(全)数学教材採用促進パンフレット「確かな学力を育てるために」を作成・配布(シリーズ2弾まで作成)。 |
|
3月 |
(社)(財)OECD(PISA)並びにIEA(TIMSS)の学力調査に関する編集者研修会を開催。 |
|
5月 |
(社)機関紙「図書教材新報」リニューアルして再刊。 |
|
6月 |
(財)「授業と教材−教材の正しい理解と活用のために」三訂版を刊行。  初任研テキスト「授業と教材」
初任研テキスト「授業と教材」三訂版 |
|
7月 |
(全)構造改革委員会、報告書を作成・配布。 
構造改革委員会 報告書 |
|
9月 |
(社)東京、大阪で中学校営業社員研修会を開催。 |
|
|
(全)宮崎の台風14号の風水害に際し、加盟社に呼び掛け、教材を無償提供。 |
||
| 2006(平成18)年 | 1月 |
(社)協会ホームページを刷新。 |
|
(全)教材採用をお願いする宣伝パンフレット「子どもをのばす教材力」を作成・配布(以下、シリーズ化)。 |
||
3月 |
(社)NPO法人日本文藝著作権センターと提携して、第2回教材に関する文芸著作物使用に関する編集者研修会を開催。 |
|
12月 |
◇教育基本法が全面改正。 |
|
| 2007(平成19)年 | 1月 |
(社)日本文藝家協会、日本児童文芸家協会、日本児童文学者協会との間で「音読CD、ネット配信型教材、デジタル教材の取り扱いについて」を締結。 |
4月 |
(学)日本教材学会の会長に川野邊敏氏が就任。 | |
5月 |
機関紙「図書教材新報」をA4に拡大し、増ページ。 |
|
6月 |
◇教育基本法の全面改正を受けて、教育関連三法(学校教育法、教員免許法、地方教育行政法)が大幅改正。 |
|
| 2008(平成20)年 | 5月 |
(全)若い教師向けの採用促進パンフレット「子どもをのばす教材」(小学校用・中学校用)を作成・配布。以後、シリーズ4弾まで作成。 |
6月 |
(全)岩手・宮城内陸地震に際し、加盟社に呼び掛け、教材を無償提供。 |
|
7月 |
(社)創立50周年記念式典を開催。 
創立50周年記念式典 |
|
9月 |
(社)(財)学習指導要領の趣旨を徹底するための編集者講習会(小学校・中学校)を開催。 |
|
10月 |
(社)業務委員会を設置。 |
|
|
(社)公益法人制度改革検討委員会を設置。 |
||
|
(全)「−学校直販教材業界−販売店のための関係法令解説」を作成・配布。 |
||
11月 |
(学)設立20周年記念研究発表大会を開催。合わせて、記念論文集『教材学』を刊行。 |
|
12月 |
◇公益法人制度改革関連3法が施行。公益法人のあり方、及び申請方法等が大きく変わる。 |
|
| 2009(平成21)年 | 3月 |
(社)業界ネットワークWeb発注システム稼動開始。 |
5月 |
(全)法人化実行委員会を設置。一般社団法人化に向けて研究協議。 |
|
9月 |
(社)第1回「子どもとことばの力」フォーラムを開催。 |
|
10月 |
(財)岐阜女子大学と提携して、学校教育支援コーディネーター養成講座(基礎講座)を開催。 |
|
11月 |
(社)第2回「子どもとことばの力」フォーラムを開催。 |
|
|
(全)全小会議と小学校加盟出版社で全販協50周年マークを作成・配布。新学期見本袋へ印刷。 |
||
12月 |
(財)岐阜女子大学と提携して、学校教育支援コーディネーター養成講座(実践・課題別講座)を開催。講座終了後、学校教育支援コーディネーター検定試験を実施。 |
|
| 2010(平成22)年 | 1月 |
(社)教学図書協会との間で「教科書準拠教材への教科書利用に関する基本契約書」を大幅改定。 |
6月 |
(全)全国図書教材販売協議会、法人化のための法制度上の解散。 |
|
|
(全)リサイクルシステムReCo事業を中止。 |
||
7月 |
(社)(財)学習評価及び新指導要録についての編集者研修会を開催。 |
|
9月 |
(全)一般社団法人全国図書教材協議会設立。 |
|
10月 |
(社)第3回「子どもとことばの力」フォーラムを開催。 |
|
| 2011(平成23)年 | 3月 |
(全)東日本大震災被災に際し、加盟社に呼び掛け、教材を無償提供。合わせて、東日本大震災義援金を実施。 |
8月 |
(社)(財)図書教材研究センターが日本図書教材協会に吸収合併。 |
|
|
(著)教材等著作権保護委員会を再編、委員長に前田哲男弁護士が就任。 |
||
10月 |
(社)デジタル教育に関する研修会(第1回)を開催。 |
|
12月 |
(全)東日本大震災教育復興支援制度を2年間限定で実施。 |
|
| 2012(平成22)年 | 1月 |
(社)(財)第4回「子どもとことばの力」フォーラムを仙台で開催。 |
日本図書教材協会
| 歴 代 会 長 |
|---|
| 1955(S30)8月〜1985(S60)7月 挾間 茂 |
| 1985(S60)8月〜1986(S61)7月 中野 人士(代行) |
| 1986(S61)8月〜1996(H8)7月 杉江 清 |
| 1996(H8)8月〜2001(H13)7月 柳川 覚治 |
| 2001(H13)8月〜 菱村 幸彦 |
全国図書教材協議会
(2010年8月までは全国図書教材販売協議会)
| 歴 代 会 長 |
|---|
| 1958(S33)8月〜1964(S39)6月 挾間 茂 |
| 1964(S39)7月〜1996(H8)6月 坂根 哲夫 |
| 1996(H8)7月〜2010(H22)8月 清水 厚實 1997年3月までは代行 |
| 2010(H22)9月〜 佐野 金吾 |
旧 財団法人図書教材研究センター
| 歴 代 理 事 長 |
|---|
| 1968(S43)9月〜1986(S61)3月 挾間 茂 |
| 1986(S61)4月〜1993(H5)3月 中野 人士 1988年3月までは代行 |
| 1993(H5)4月〜1998(H10)3月 水谷 清吉 |
| 1998(H10)4月〜2011(H23)7月 辰野 千壽 |